このブログで何としても最初に紹介したい本!!
それは ……
「コンサル一年目が学ぶこと」だ!!! (ででん)
前に本屋へ行った時
この本で本棚1面が真っ青になってたな…
でも、自分コンサルじゃないし!
ってスルーし続けてたの、分かる人いる? (自分や!)
スルーし続けること数年、
kindle unlimitedで無料だったので いざ拝見!!
結果…
コンサルでない自分でも、いや、
コンサルでないからこそ、めちゃめちゃ満足できる内容だった。
というのもこの本、
「コンサルに限らず、全業界の社会人が持つべき本質的なスキル・マインド」
が載っている。
企業で働く社会人から、ゼミ・研究室に所属する学生まで
組織・チームで仕事をする時に意識・実践すべきこと
が具体的な方法も併せて コンパクトにまとめられている。
ぜひ一読して欲しいこの本を、以下で詳しく紹介していこう。
☆ 新入社員、もしくは社会人になって数年の人
☆ 頑張っているのに、上司や先輩からの評価がいまひとつな人
☆ 一生通用するビジネススキル・マインドを身に着けたい人
☆ 仕事のやり方をもう一度おさらいしたい人
本書の構成は以下の通りだ。
第1章 コンサル流話す技術
第2章 コンサル流思考術
第3章 コンサル流デスクワーク術
第4章 プロフェッショナル・ビジネスマインド
はじめがきから参考書類の紹介を含めて合計281ページで、
それぞれ概要と事例、実践手法を簡潔にまとめている。
特にコンサル業界では
「年次・立場が上の顧客に対し、相手の期待値を超えたプレゼンを行う」
ことが重要だ。
その顧客とは、大企業の社員だったり、時には部長・役員にまでなるわけで…
つまり、
ハイクオリティなプレゼン・資料作成を行うために
新入社員が習得すべき、論理的な話し方・思考法やテクニック
が4章に渡って記載されているのだ。
でもぶっちゃけ、
どの業界でもプレゼンなり資料作成なんてするよね?(何なら学生でも)
そう、コンサルを出た人が色んな業界で活躍しているように、
「将来どのキャリアを選んでも無駄にならないノウハウ」が詰まってるんじゃあ!!
……と私は思った。
特に
①論理的思考に関する研修が少ない
②コンサルが意識していることを網羅的に学習したい
そんな他業界のビジネスマンにはうってつけだ。
全部に触れていきたいところだが、さすがに長くなりすぎるので……
特に自分が興味を持った、期待値を超えるってどうすればいいんだろ?
ってとこを書いていく。
上司から「資料作って~!」って頼まれて、
めちゃめちゃ頑張って提出したのに、反応が微妙だった…
こんな経験ない? 自分はありまくりだ (オイ…)
なんで↑みたいなことが起きるのかっていうと、
「上司と自分とで、作りたかった資料 = 成果物 のゴールが一致していない」
ことが原因だと思うんだよね。
例えば、
「プロジェクトの課題について、資料にまとめといて」
って言われた時、これだけで「Yes! Sir!」って答えちゃいけないと思うんだ。
・その資料は顧客向けか、社内向けか
・期限はいつなのか
・習うべき資料のフォーマットはあるのか
・課題だけでいいのか、対応状況まで考えて書くべきなのか
とか聞いてからやらないと、手違い・手戻りが起こっちゃうんだよなぁ (戒め…)。
つまり、
作業の目的とかクオリティとか、
相手が求めている成果を理解してないと、そもそも相手の期待値を上回れない
って前提があるんだと。
この本だと、
・作業に取り掛かる前に確認すべき点
・成果に行き着くまでの思考プロセス
・+αで自分なりの提案をする方法
が具体的に書かれてる。
もし自分みたいに、「上司の要求にクリティカルに答えられない!!」という悩みを持ってたら、
解決の一助となるかもしれない。
<br>
・コンサルの持つ「ロジカル思考法・資料作成テクニック・マインド」が網羅されている
・作業に取り組む前に、相手の期待値を正確に把握することが大事
また本記事ではあまり触れなかったが、第3章・第4章の概要は以下の通りだ。
第3章:議事録・Office365 (パワポ・エクセル) の作成術、読書(情報検索)術
第4章:マインド面 (チームワーク、仕事への向き合い方など)
以上、「コンサル一年目が学ぶこと (著:大石哲之)」の紹介だ。
全ビジネスパーソンの土台にふさわしい本なので、気になった人は是非読んでみてくれ。
※ちなみに、「図解 コンサル一年目が学ぶこと (著:大石哲之)」なんて本もあるらしい。
こちらは読んだことはないので、参考として紹介させていただく。
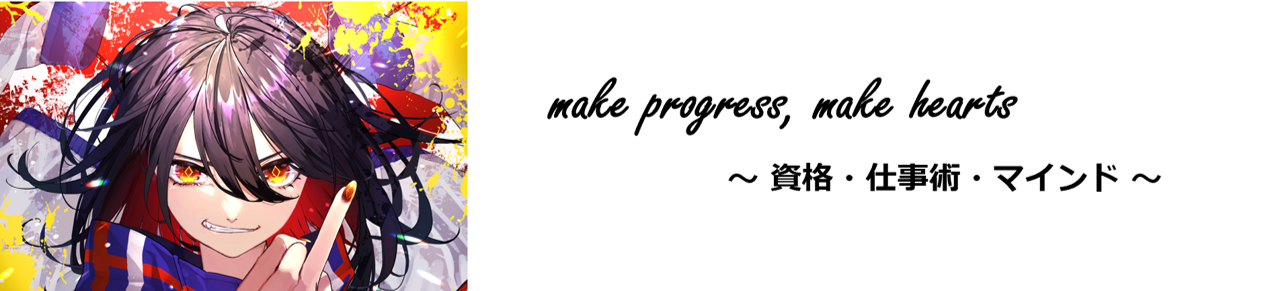


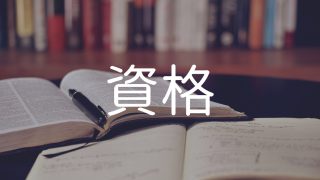
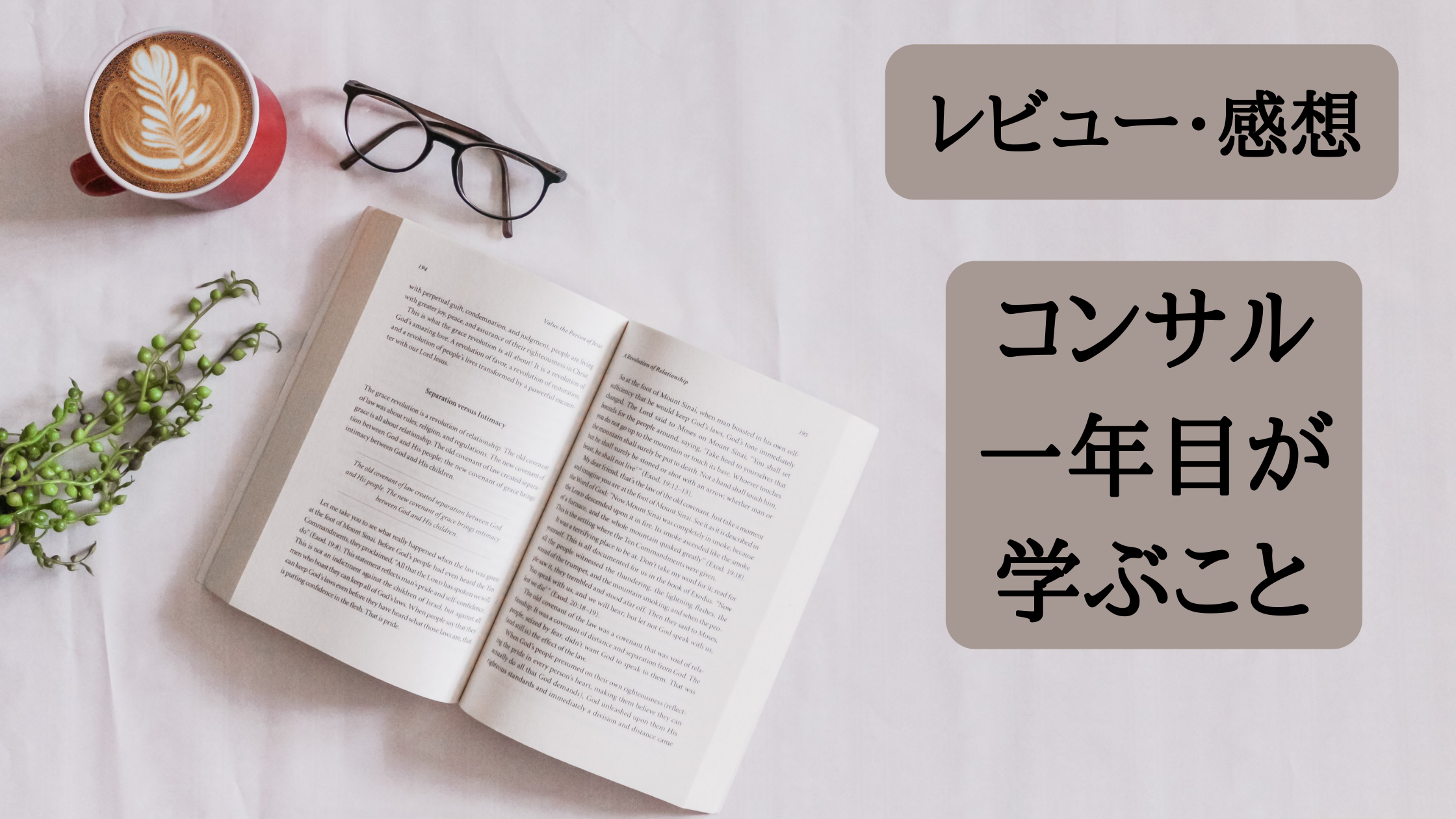


コメント